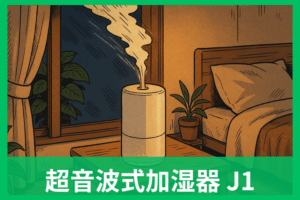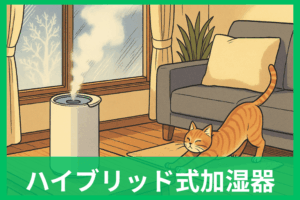「肉汁」をなんと読みますか?
“にくじゅう”派も“にくじる”派もいますよね。
本記事は、検索で最も多い疑問「どっちが正しいの?」に最短距離で答えます。
結論はシンプル。フォーマルは「にくじゅう」、日常は「にくじる」もOK。
辞書・放送の基準と、実際の使われ方を簡潔に整理したので、仕事の文書でもSNSでも迷わなくなります。
今日からあなたも自信を持って使い分けられるはずです。
肉汁の読み方、本来の正解はどっち?
漢字熟語の読み方ルール(音読みの原則)
漢字の組み合わせは、基本的に「音読み+音読み」で読むのがスタンダードです。
たとえば「肉(にく)」は音読み、「汁(じゅう)」も本来は音読みなので、古くからの原則にあてはめると「肉汁=にくじゅう」になります。
逆に「にくじる」は上が音読み、下が訓読みという“重箱読み”の形。重箱読み自体は日本語でよくある現象ですが、伝統的・辞書的な立て付けでは「にくじゅう」が先に来る――ここが理解の出発点です。
言い換えると、「にくじゅう」はルールに沿った読み、「にくじる」は慣用として広まった読み、という整理がしっくりきます。
伝統的に放送の現場でも「ニクジュー(=にくじゅう)」を基本とする運用が長く続いてきました。
「にくじゅう」とされる理由
「にくじゅう」を推す根拠はシンプルです。
①熟語の原則(音読み同士)に沿う
②主要な国語辞典の多くが主見出しを「にくじゅう」に置いてきた
この二つです。
さらに、NHKなどの放送指針も長らく「ニクジュー」を第一とする運用で、公式の場やアナウンスでは「にくじゅう」が“まず推奨”と整理されてきました。
もっとも近年は例外も増えていますが、フォーマルな文書・校正の観点では今も「にくじゅう」が無難。
つまり“正統派の第1候補”が「にくじゅう」、そんなイメージで覚えておくと迷いにくいです。
「にくじる」が広まった背景
一方で「にくじる」も一気に広まりました。
理由は大きく三つ。
①「汁=しる」という日常語の強さ(“みそ汁=みそしる”の延長で自然に読まれやすい)
②「肉厚・肉太」など“肉+訓読み”の言い回しに引っぱられる心理
③テレビやネットの影響で耳にする機会が増え、違和感が減ったこと
NHKの「ことばのゆれ調査」(2000年11月)では「にくじる」と読む人が71%に上り、その結果、翌2001年の放送用語委員会で「にくじる」も“第2候補”として認める運用に改められました。
社会での使用が実態として多数派になった、というわけです。
辞書ではどう書かれている?
広辞苑・大辞泉・大辞林の扱いの違い
国語辞典の多くは、見出しの第一に「にくじゅう」を置き、「(にくじるとも)」のように注記で触れる構成です。
小学館「デジタル大辞泉」でも、語義3(肉を焼いたときにしみ出る液汁)の欄に「(にくじるとも)」と明記され、併記の関係がわかります。
つまり辞書は“原則はにくじゅう、ただし使用実態に応じてにくじるも許容”という立場が主流。
実務ではこれが校閲の基準にもなりやすく、媒体の表記ルールに合わせてどちらかに統一する――そんな運用が一般的です。
ジャパンナレッジの要点
辞書横断プラットフォームのジャパンナレッジでも、「『にくじる』は重箱読みで新しい言い方」と整理されます。
加えて、放送の場では伝統的な「ニクジュウ」を用いる方針が紹介されており、読み分けの位置づけが簡潔にまとまっています。
ここまでを踏まえると、辞書界隈の共通認識は「第一はにくじゅう、ただしにくじるも慣用として広く通用」に収れんしていると言えます。
迷ったら“媒体の基準に合わせる”が実務的な正解です。
「にくじる」が定着したワケ
「汁=しる」の連想と発音しやすさ
「汁」を日常で読むとき、ほとんどの人は「しる」と発音します。
だから「肉+汁」を見ると、条件反射的に「にくじる」と口が動く――この“連想の強さ”が最大の要因です。
さらに「にくじる」は母音のつながりが滑らかで、言いにくさが少ないのも定着を後押ししました。
似たパターンはほかにもあり、上の字が音読み、下が訓読みになる重箱読みが口語で広がる例はめずらしくありません。
こうした“言いやすさ”と“生活語の影響”が、教科書的な原則を上書きしていくのは、日本語の自然な変化の一つと言えます。
慣用として広がった経緯
2000年前後にはグルメ番組・情報番組が一気に増え、「肉汁」という語が“おいしさの記号”として連呼されました。
アナウンサーやナレーターも場面や視聴者層に応じて読みを選び、結果として「にくじる」が耳に残る機会が急増。
前述のNHK調査で“多数派”が可視化され、放送用語委員会が“両にらみ”の運用を決定。
以後は雑誌・Webでも「どちらも可」を前提に、媒体ごとの表記ガイドに従って統一するやり方が定着しました。
こうして“実態に合わせた許容”が制度面でも裏づけられ、一般の会話では「にくじる」が日常的に使われるようになった、という流れです。
実際の使われ方とメディアの運用
NHKの調査と放送現場の方針
NHKの「ことばのゆれ調査」(2000年11月)では「にくじる」が71%という結果が紹介され、これを受けて2001年2月の放送用語委員会が「第1=ニクジュー/第2=ニクジル」と整理。
実際の放送では“まず第1の語形を推奨”という原則があるため、ニュースや解説のようなフォーマル寄りの場面では今も「ニクジュー」優先、グルメ番組などでは文脈に応じて「ニクジル」も使われる、という運用が落ち着きどころになっています。
現場のナレーターやアナウンサーの証言も、この方針と整合しています。
新聞・テレビ・会話での選択
新聞・雑誌・Webの多くは、ハウスルールに従い「にくじゅう」で統一する媒体が目立ちます。
一方、読者に寄り添う生活情報系・女性誌・トレンド媒体では「にくじる」も積極的に紹介され、辞書の注記を併記する記事も少なくありません。
テレビでは番組の雰囲気に合わせて“わかりやすさ優先”で選ばれ、日常会話では「にくじる」が実質の多数派――そんな使い分けが現状です。
要は、フォーマル度・受け手・媒体方針の三つで読みが決まると考えるとブレません。
結論:どう使い分ける?
フォーマルは「にくじゅう」、日常会話は「にくじる」もOK
結論を一言で:かしこまった場では「にくじゅう」、ふだんの会話やグルメ文脈では「にくじる」もOK。
履歴書・論文・企業サイト・ニュース原稿など“正確さ”と“伝統的表記”が求められる文脈では「にくじゅう」を採用するのが安全です。
対して、SNS・口コミ・飲食レビューのように“話し言葉に近い”場では「にくじる」でもまったく問題ありません。
この使い分けは辞書と放送の双方の基準に沿っており、読み違いだと指摘されるリスクを最小化できます。
迷ったら文脈で判断するコツ
迷ったら次の三点で即決しましょう。
① 相手(上司・顧客・一般視聴者?)
② 媒体(公的文書・ニュース・雑誌・SNS?)
③ 場の雰囲気(厳密さ重視か、軽やかさ重視か)
この三つが“フォーマル寄り”なら「にくじゅう」、カジュアル寄りなら「にくじる」。
さらに社内・媒体のスタイルガイドがあるならそれに合わせる――これが一番スマートです。
覚えておくべき土台は「辞書は第1ににくじゅう、ただしにくじるも広く許容」という事実。
これだけでほとんどの場面は乗り切れます。
まとめ
- 歴史・原則上は「にくじゅう」が第1候補。辞書・放送でも“まず推奨”。
- 実態としては「にくじる」も多数派で通用し、2001年以降は放送でも許容。
- 使い分けの軸はフォーマル度・媒体・相手。迷ったら「にくじゅう」。カジュアルなら「にくじる」も自然。
- 辞書記述(大辞泉)では語義の一部に「(にくじるとも)」の注記。
【参考サイト】
・「肉汁」の読み | ことば(放送用語) – 放送現場の疑問・視聴者の疑問 | NHK放送文化研究所
・コトバンク