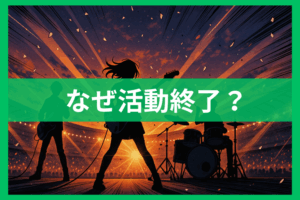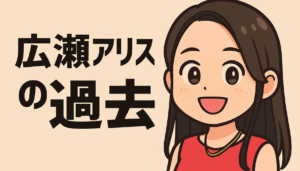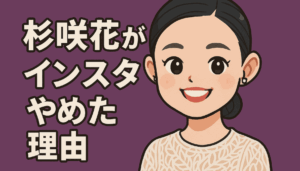「チョコプラ松尾が“素人はSNSやるな”と言ったらしい」
SNSの短い断片だけでは、背景も意図も見えません。
本記事では、実際の動画で何が語られ、どこが切り抜かれて広まったのかを一次情報ベースで丁寧に整理。
さらに、炎上が起こる仕組みと対処のコツまで、やさしい言葉でまとめました。
検索のゴールは“真相にたどり着くこと”。噂ではなく事実から、モヤモヤをスッキリさせましょう。
チョコプラ松尾の炎上エピソードを振り返る
炎上のきっかけと背景
今回の話題は、お笑いコンビ・アインシュタイン稲田直樹さんのInstagramが不正アクセス被害に遭い、警視庁が2025年9月5日に32歳の男を不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕したという報道が大きな転機になりました。
報道各社は「2024年7〜10月に不正アクセスが繰り返された」と伝えています。これにより、稲田さんに向けていた疑いの一部が「乗っ取り」による可能性へと再評価され、ネットの空気が一気に変わりました。
その直後、チョコレートプラネットのサブチャンネルで9月10日に公開されたトーク動画で、松尾駿さんが“強い言葉”を用いてSNSの問題点を語り、切り抜きで拡散されて炎上しました。
時系列で見ると「逮捕報道→動画での問題提起→拡散・炎上」という流れです。
批判と擁護が分かれたポイント
批判の中心は「一般人を見下している」「発信の自由を否定しているのでは」という受け止めでした。
一方で、「誹謗中傷や犯罪的行為を減らしたいという主旨だろう」「文脈を無視した切り取りだ」という擁護も少なくありませんでした。
実際の報道記事には、問題の発言だけでなく“前段の怒りの理由”やコンビでのやり取りまでが記されており、評価が割れた背景が読み取れます。
動画の削除と世間の反応
問題の動画はサブチャンネル「チョコプラのウラ」で公開されたのち、9月16日までに非公開(削除)となりました。
大手メディアは「非公開化の公式説明は確認できない」と伝え、ネット上では「言葉が強すぎた」「文脈を補足すべきだった」など賛否が続きました。
ニュースまとめや配信プラットフォームでも、該当フレーズとともに“削除済み”の扱いが広がっています。
問題となった動画の具体的な内容
発言が飛び出した文脈
動画ではまず、稲田さんのアカウント乗っ取り逮捕報道に触れ、二人が誹謗中傷やアカウント犯罪への怒りを表明しました。
松尾さんは「犯人は一生電子機器を使えない生活にしてほしい」と苛立ちを露わにし、続けてSNS全体のあり方へ議論を広げました。
ここで「素人はSNSをやるな」「素人が何を発信しているのか」といった強い言い回しが出て、そこだけが切り取られて広く拡散されたのが実情です。
全文脈は“誹謗中傷と犯罪抑止”の話題から始まっていました。
長田との掛け合いとニュアンス
相方の長田庄平さんは、松尾さんの極端な提案に「それだと何も流行らないじゃん? ただのブログじゃん」とブレーキをかける役回り。
これに対して松尾さんは「見てりゃいい」とさらに強い言い回しを重ねました。
コンビの掛け合いとしては、松尾さんが“暴走気味の本音”を投げ、長田さんが常識目線で制動する構図。
記事ではこのやり取りが具体的に記録されており、単独の断言よりも“議論の途中の強い表現”だったことがうかがえます。
「免許制」発言の真意
松尾さんは「SNSは免許制にすればいい。車と一緒で講習を受けて使うSNSがあってもいい」と述べています。
現実の制度として直ちに実装できる話ではありませんが、誹謗中傷やなりすまし被害の多発を前に「リテラシー担保」の極論を提示した形です。
なお、逮捕報道では“複数回の不正アクセス”が指摘され、SNSの脆弱さとユーザー側の対策不足が課題として浮き彫りになっていました。
こうした流れと合わせると、発言の根は“加害抑止”にありますが、言葉が強すぎたために誤読・反発を招いたと言えます。
拡散された情報と実際の差異
拡散で強調された言葉
X(旧Twitter)やニュースアグリゲーターで特に広まったのは「芸能人・アスリート以外はSNSやるな」「素人が何発信してんだ」という刺激的な部分でした。
見出しや切り抜き投稿は、短く強いフレーズに集中するため、前後の説明が落ちやすいのが現実です。
実際、J-CASTの記事でも該当フレーズは引用され、これが“炎上の顔”として独り歩きしました。
動画全体のトーンとの違い
動画全体では、稲田さんの件を踏まえて「誹謗中傷や不正アクセスは許されない」という怒りと、SNSの負の側面をどう減らすかという問題提起が軸でした。
つまり“誰でも発信するな”という恒常的な主張ではなく、“過激な言い回しを交えた議論の途中”で出たアイデアです。
第三者のコメントでも「文脈ごと見れば気の毒な面もある」という評価が示されています。
切り抜き文化が生んだ誤解
現代の情報流通は、短い動画・キャプチャ・見出しが中心です。
強い言葉はアルゴリズムと相性が良く、真っ先に拡散されます。結果として“発言の目的”より“語気の強さ”が先行し、差異が拡大します。
今回も、全体の文脈よりも「素人」という言葉の上下関係を感じさせる響きが強く、誤解や反発が加速しました。
専門家やメディアの検証が入る前に、評価が固まってしまう典型例です。
炎上後の松尾・周辺への影響
動画削除とその後の動き
9月16日までに該当動画は非公開化。
報道では、公開側からの詳しい説明は確認できないとされています。
非公開後も、まとめ記事や掲示板では切り抜き文言が引用され続け、二次・三次の拡散が継続。
いわば“動画は消えても言葉は残る”状態になりました。
世論の温度差とメディア報道
ネット世論は大きく二極化しました。
「見下しだ」とする批判と、「誹謗中傷に限った文脈の話」とする擁護です。
J-CASTの続報では、茂木健一郎氏が「切り取りで可哀想な面も」と文脈を踏まえた見解を示し、議論は“表現の強さ”と“被害抑止”のバランスへ移っていきました。
今後のリスクとチャンス
短期的には、スポンサーや番組側が“言葉選び”に敏感になり、出演者のリスク管理が強化されるでしょう。
一方で、今回を機にネットリテラシーや通報・証拠保存、二段階認証といった具体策を芸人側から発信するチャンスもあります。
実際、乗っ取り事件の報道は「複数回の不正アクセス」「パスワード推測の可能性」など実務的な課題を可視化しました。
コンテンツ発信者が“守り方”を共有する流れは、ファンとの信頼強化にもつながります。
芸人の炎上リスクとSNS文化
「笑い」と「不快感」の境界線
芸人の表現は誇張や皮肉を伴いますが、切り抜きに耐える“安全マージン”がない言葉は、文脈から切り離された瞬間に不快へ傾きやすいのが現実です。
特に「素人」「一般人」など広い層を一括りにする語は、上下関係を想像させるため、反発を呼びがち。
今回のように“前段の怒り”があっても、短いテキストや数十秒の動画では前提が抜け落ち、メッセージの芯よりも語気がフォーカスされます。
この“文脈損失”は炎上リスクの核心です。
炎上を避けるための自衛策
発信前に「誤読の起点」になりやすい箇所を洗い出し、言い換えや注釈テロップで前提を固定するのが効果的です。
強い主張をするなら、誰に対して・何の行為を止めたいのかを“行為ベース”で特定すること(例:誹謗中傷・不正アクセス・なりすまし)。
公開後はタイトルやサムネにも誤誘導がないかを点検し、切り抜きガイドラインや許諾範囲を明示するのも一手。
技術面では二段階認証やパスワード管理、ログ監視を基本装備に。
乗っ取り事件の例が示す通り、加害の入口は意外と単純な推測・流出にあります。
今後の芸人・SNSの関わり方
「免許制」のような極論は議論の呼び水になりますが、現実解はプラットフォームのラベリング強化、悪質行為の報告→処置の透明化、AI時代のなりすまし検知などの運用改善でしょう。
発信者側は、批判と対話を分けて受け止め、建設的な意見には感謝と反映、悪質行為にはスクショ保存と通報・法的対応で臨む“二層対応”を徹底する。
こうした姿勢が、炎上を“消耗戦”から“学びの場”へ変える第一歩になります。
チョコプラ松尾の「失言」と炎上の真意まとめ
要点を整理すると、①2025年9月5日の不正アクセス逮捕報道で空気が変わる→②9月10日のサブチャン動画で松尾さんが強い表現を使用→③「素人〜」部分だけが切り抜きで拡散→④9月16日までに動画は非公開、という流れでした。
文脈全体は“誹謗中傷や犯罪抑止”の問題提起ですが、強い言葉が前面化して「一般人を排除」と読める余地を生み、差異が拡大したのが今回の本質です。
事実関係はJ-CASTの逐語的な引用と、朝日・毎日・民放各局などの逮捕報道で裏取りできます。
フェアに言えば、「拡散での誇張」と「元の言葉の強さ」が重なって炎上した、という結論になります。