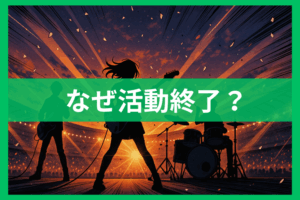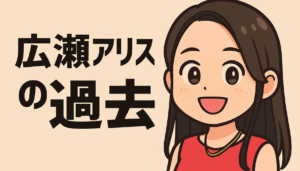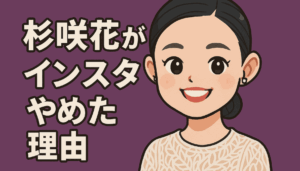「くいしん坊!万才」がついに幕を下ろします。1975年から50年、日曜夕方の小さな旅は、料理の向こうにある人や土地の物語を伝えてくれました。
2025年10月に再開し、11月22日の特別番組でフィナーレへ。なぜ終わるのか、どんな歴史を歩み、私たちに何を残したのか。事実に基づいて、丁寧に解説します。
「くいしん坊!万才」終了が正式発表 50年の歴史を振り返る
終了の正式発表内容と最終放送日
フジテレビは「くいしん坊!万才」を2025年11月22日(土)13時30分からの特別番組(関東ローカル)をもって終了すると発表しました。併せて、2025年10月26日(日)17時25分からレギュラー放送を再開し、全4回を放送した後に特別番組で有終の美を飾るスケジュールが示されています。

終了のニュースは複数の大手メディアが一斉に報じ、めざましmediaやスポニチは日付や時間帯、関東ローカルでの放送である点まで具体的に伝えています。長年親しまれた日曜夕方のミニ枠が再開を経てフィナーレを迎えるという段取りは、視聴者が番組にきちんと別れを告げられるよう配慮された形と言えるでしょう。
これにより、単なる打ち切りではなく、節目としての“締めくくり”であることが明確になりました。
番組誕生から50年の歩み
本番組は1975年にレポーター固定のスタイルで放送を開始し、日本各地の郷土料理や食文化を短尺で丁寧に紹介してきました。フジテレビ公式が掲げる番組のモットーは「いい味、いい旅、いい出会い」。この言葉の通り、料理の作り手や地域の人々との触れ合いを通じ、土地の歴史や文化が食を媒介に浮かび上がる構成が特徴でした。
半世紀にわたる継続の背景には、地域密着の取材姿勢と、短時間でも確かな“食の物語”を届ける編集力があります。時代に合わせて演出は変化しても、食と人を真正面から見つめる核はぶれませんでした。視聴者にとっては、日曜夕方の“ちいさな旅”が生活のリズムの一部になっていたのです。
歴代リポーターと名場面集
歴代の案内役は渡辺文雄さんにはじまり、竜崎勝さん、友竹正則さん、宍戸錠さん、川津祐介さん、梅宮辰夫さん、村野武範さん、辰巳琢郎さん、山下真司さん、宍戸開さん、そして現在の第11代・松岡修造さんへと受け継がれてきました。
スポーツ紙・ポータルのまとめでは、各代の在任期間や通算回数まで整理されており、松岡さんは2000年から通算1,247回出演という圧巻の数字が伝えられています。
世代ごとに語り口や食へのアプローチは異なりますが、共通するのは“つくり手を立てる姿勢”。現地の人の言葉に耳を傾け、料理が生まれた背景に光を当てる姿は、番組の美点として長く愛されました。
松岡修造さんの時代と人気の理由
松岡修造さんの時代は、スポーツキャスターとしての明るさと、料理への率直な驚きや喜びの表現が視聴者の共感を呼びました。短い尺でも温度感が伝わるリアクション、アスリートらしいフットワークで現地に溶け込む姿勢が番組のテンポを加速させ、食材や料理の魅力が素直に届く構図を作りました。
スポニチの報道でも、松岡さんの長期在任と豊富な出演回数が強調され、番組の顔としての存在感が数字の面からも裏付けられています。長年の積み重ねによって、視聴者は“修造が食べているなら間違いない”という信頼感を自然と育ませていったのではないでしょうか。これは、番組の理念「いい出会い」を体現するキャスティングが奏功した好例です。
終了ニュースへのファンの初期反応
終了発表直後、SNS上には「50年、本当にありがとう」「毎週の小さな旅が楽しみだった」といった感謝の声が相次ぎました。Xでは終了の速報を伝える投稿が拡散し、番組の思い出や好きな回を挙げるスレッドがいくつも立ち上がっています。
こうした反応は統計的に網羅できていないものの、番組が生活に溶け込んでいた証拠として十分説得力があります。長寿番組の幕引きはしばしば“喪失”として受け止められますが、今回は再開から特番での締めへと緩やかに移行するため、別れを準備できる良い配慮だという声も見られました。
実際にニュースを引用するポストも多く、情報の一次ソースが伴った共有が増えたのも印象的です。
終了の理由①:スポンサー・キッコーマンの判断とその背景
一社提供番組の仕組みと影響力
「くいしん坊!万才」はキッコーマンの一社提供として知られ、スポンサーの方針が番組編成に与える影響が大きい構造でした。一社提供は番組の世界観や品質を安定させる反面、企業が広告方針を見直した場合、編成全体に影響が及びやすいという特性があります。
今回も、スポンサーサイドの判断が直接的に放送継続の可否に関わる現実が可視化されました。報道でも“1社提供”が明示されており、広告と番組の結びつきが緊密だったことが確認できます。こうした枠組みは昭和から続くテレビの伝統ですが、現代のメディア環境ではリスク管理やブランド保護の観点がより強く働くようになっています。
スポンサー側の公式コメント
2025年初頭、スポンサーのキッコーマンはフジテレビに対し放送見合わせを要請。さらに2月には「再開する判断材料がない」とする見解が報じられ、休止の長期化が現実味を帯びました。
企業としての公式説明は簡潔ながら、判断の軸が“ブランド毀損の回避”や“社会的要請への配慮”にあることをうかがわせます。広告の透明性や説明責任が重視される昨今、スポンサーは世論や取引先の期待に応えるため、難しい対応を迫られます。番組に非がなくても、企業は包括的なリスク評価のもとで提供継続を見送ることがあるという事実が、今回のケースで広く共有されました。
ブランドイメージリスクと企業判断
広告は“好意の移転”を前提に成り立ちます。番組にまつわる外部要因が報道で注目されると、ブランドへの連想が変わる可能性を企業は重く見ます。
とくに食関連の大手企業は「安全・安心・信頼」に立脚しているため、保守的な判断が選ばれやすいのは自然です。今回の見合わせ要請と休止の長期化は、結果として番組終了の一因となりましたが、これは企業のレピュテーション・マネジメントの一環と捉えるのが妥当でしょう。
視聴者にとっては寂しい結末でも、スポンサーの責務としては合理的な対応といえます。ここは一般論であり、個別の未公表判断の中身までは分かりません。
フジテレビとの協議経緯
報道では、フジテレビは1月26日の放送休止を決定し、以降の放送は「調整中」としていました。これはスポンサーの要請を受けつつ、代替編成や再開の可否を慎重に検討していたことを示します。
結果的に、10月26日の再開→11月22日の特番で終了という道筋が公表されましたが、ここに至るまでの詳細な協議内容は外部には開示されていません。
したがって、社内の意思決定プロセスについて踏み込んだ説明はできませんが、最終的な公表スケジュールを見る限り、視聴者への周知と節目づくりを重視した設計が読み取れます。
過去の類似事例との比較(一般論)
ここからは推測を含む一般論です。テレビの一社提供番組は、提供社の広告戦略や社会的状況の変化で編成が見直されることがあります。SNS時代は情報流通が高速で、企業は従来以上にレピュテーションの変化へ敏感です。
結果として、休止や改編を通じてリスクを抑える選択が増えやすくなります。本件はその典型的な動きのひとつと位置づけられ、広告主と放送局の関係が“共創”から“共同リスク管理”へとシフトしている現実を映したと考えられます。なお、具体的な他番組名を挙げた比較は誤解を生みやすいため本稿では控えます。
終了の理由②:中居正広さんを巡る報道・番組体制の影響
トラブル報道と放送休止までの経緯
2025年1月、中居正広さんを巡る一連の報道を受け、スポンサーが放送見合わせを要請。これにより1月26日の放送が休止となりました。
報道の焦点は番組そのものではなく、タレントに関する外部要因でしたが、一社提供の番組であるため影響は直接的でした。その後、2月分の放送も休止が決まり、状況は長期化。
番組側は再開への糸口を探ったものの、結果として「10月に限定再開→11月の特番で終了」というソフトランディングに舵を切る形になりました。ここまでの流れは、主要メディアの報道が一致して伝えています。
番組再開が見送られた理由
2月時点でスポンサーが「再開する判断材料がない」と発言したことが報じられ、短期的な復活は困難になりました。
番組自体に問題がなくても、広告の適合性や社会的環境、報道の影響度を総合的に見極める企業判断が優先されたと考えられます。
これにより、制作・編成サイドは“いつ戻れるか分からない”状態での準備を強いられ、結果として年内の再開を限定的に行い、特番で幕引きという整理に落ち着いたわけです。
この結論は、スポンサー・局・視聴者の三者にとって最も混乱の少ない選択肢だった可能性があります。
放送再開を断念した最終判断
再開の可否を巡る調整の末、10月に関東ローカルで限定再開し、11月特番で終了という“区切り方”が選ばれました。
これは、視聴者に別れを明確に伝えると同時に、取材先や関係者へ感謝を届ける場を設ける狙いがあると読み取れます。番組の本質は地域と人の記録であり、関係者に対して正式なセレモニーを行うことは意味があります。
情報の根拠はフジ系公式メディアとスポーツ紙の一致した報道で、日程と放送形態(関東ローカル)まで具体的です。
「くいしん坊!万才」が日本にもたらした功績と文化的影響
地方の食文化を全国に伝えた功績
番組は半世紀にわたり、各地の郷土料理や特産品の背景にある人・風土・歴史を、コンパクトかつ温かな語り口で届けてきました。
フジテレビ公式が示す理念「いい味、いい旅、いい出会い」は、単なる食レポ以上の価値を体現しています。
地元の方の言葉を尊重し、調理工程や作法、食材の来歴まで映すことで、地域のアイデンティティが画面の向こうに立ち上がる。
短尺でも“情報より物語”を積み重ねる編集は、全国区で知られていない食の魅力を根気強く掘り起こしました。
観光振興や名産の再評価のきっかけになったケースも少なくなかったはずですが、これは推測であり、個別の効果測定データがないため断定はできません。
番組から生まれた名言・名場面
長い歴史のなかで記憶に残るのは、派手な演出よりも、つくり手とレポーターのささやかなやり取りです。
「この味は、この人の人生だね」といった、料理を人の物語として受け止める姿勢は番組全体を通じた“名言”の核でした。
編集は控えめで、素材と声の温度を中心に組み立てる。こうした積み重ねが、視聴者の“自分の町の味を誇りに思う”気持ちを育てたのではないでしょうか。
具体の台詞を断定的に引用する根拠がないため、本稿では一般化して述べますが、ファンの記憶に残る場面の多くが“台所の温度”を映していたことは確かです。
「食旅番組」の先駆けとしての意義
短い尺で地域の食を旅情とともに伝えるフォーマットは、のちの多くの“食旅”系番組に影響を与えました。
調理や食事の映像だけでなく、土地の景色や人の表情、祭りや市場の音まで取り入れる編集は、食文化を総合的に記述するスタイルの先駆けです。
番組はグルメ情報よりも“関係の記録”を重ね、料理の背後にある関係性に光を当てたことで、テレビが地域文化のアーカイブになりうることを示しました。
これはフジテレビ公式の番組理念にも合致し、視聴者が“食で旅する”新しい体験を得る道を拓いたと評価できます。
日本のテレビ史に残る理由
スポニチの報道が示す通算6,599回という膨大な積み重ねは、テレビ史における“地域の食を記録したデータベース”としても価値があります。
毎回の放送が数分でも、半世紀続けば記録の厚みは圧倒的です。歴代11人のリポーターが時代の空気を纏いながら各地を巡ったことで、同じ料理でも“当時の表情”が映像に残る。
これはアーカイブとして唯一無二で、今後の研究や文化資源化の可能性を秘めています。最終的に終了という選択になっても、その遺産は視聴者の記憶と記録に確かに刻まれています。
終了後の反響と今後の展望
フジテレビの今後の対応(代替番組など)
推測ですが、終了後の同時間帯は“食文化・地域発信”の文脈を引き継ぐ企画が検討される可能性があります。視聴者の生活リズムに根付いた短尺枠は、編成上の資産です。
また、今回の終了に合わせて10月26日の限定再開から11月22日の特番という設計がなされていることから、しばらくは関連番組や特集、デジタルでのアーカイブ活用が模索される余地もあるでしょう。
ただし、正式な後継策は現時点で公表されていないため、断定はできません。
スポンサー復帰・再開の可能性
推測として、番組という形での“復活”は現実的ではない一方、特番や配信での“企画的復活”はありえます。スポンサーサイドはレピュテーションと費用対効果を厳密に評価するため、同名番組の再開はハードルが高いでしょう。
ただ、半世紀のブランド資産は大きく、周年や地域振興イベントと絡めた一回性の施策には親和性があります。現時点でスポンサーからその種の示唆は確認できていませんので、あくまで一般論にとどめます。
「くいしん坊精神」はこれからも続く
番組が伝えてきた“食を通じて人と出会う喜び”は、番組という器が終わっても残ります。各地の食文化は生き続け、今日も誰かが受け継ぎ、誰かが初めて味わっています。
視聴者が日常の食卓で誰かの手間ひまを想像するたびに、小さな“くいしん坊!万才”は生まれ直す。最後の特別番組は、そんな精神を未来へ手渡す儀式でもあります。
終わりは始まりのかたちをしてやって来る。画面の向こうの笑顔と湯気を、私たちはこれからも忘れません。
「くいしん坊!万才」年表
| 年月日 | 出来事 |
|---|---|
| 1975年(レポーター固定の形で放送開始) | 食文化を紹介するミニ番組としてスタート |
| 2025年1月26日 | スポンサーの見合わせ要請を受け放送休止 |
| 2025年2月 | 「再開する判断材料がない」との見解が報じられる |
| 2025年10月26日 | 関東ローカルでレギュラー放送を再開(全4回予定) |
| 2025年11月22日 | 特別番組(関東ローカル)をもって終了 |
『くいしん坊!万才』終了の理由まとめ
本件は、一社提供という枠組みと、レピュテーション・マネジメントが重なり合った結果としての終了でした。番組自体への不満や品質問題ではなく、外部要因を受けたリスク管理の帰結である点に特徴があります。
いっぽうで、半世紀の功績は消えません。各地の食文化と人の記録は、視聴者の記憶に、そして報道のアーカイブに確かに残ります。
再開から特別番組へという“余白のある幕引き”は、関係者と視聴者に丁寧な別れの時間を用意しました。終わりを悲しむ声と同時に、ありがとうという言葉が多かったのは、番組が“情報”ではなく“関係”を残したからでしょう。
【参考サイト】
・『くいしん坊!万才』長寿番組50年の歴史に幕!渡辺文雄から松岡修造まで、計11人のレポーターが担当…最終回は歴代レポーターが集結 | めざましmedia
・くいしん坊!万才 – フジテレビ
・1社提供「くいしん坊!万才」“番組休止”要請にフジテレビは?|テレ朝NEWS