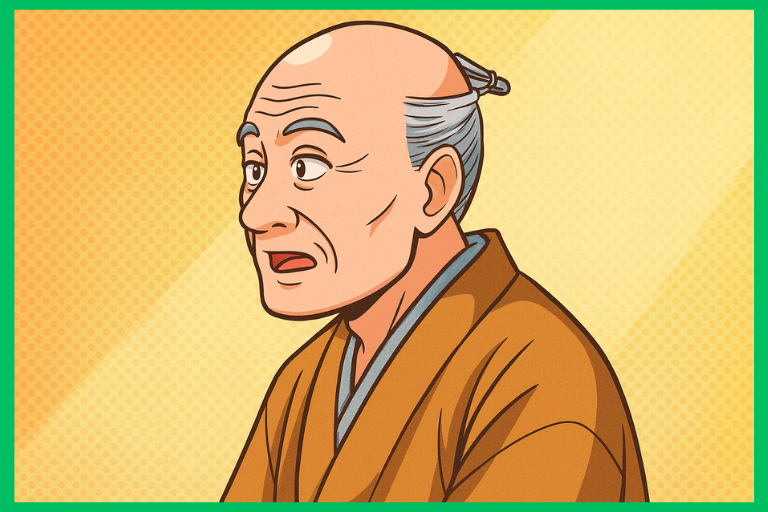「江戸時代の文人」と聞いて、あなたはどんな人を想像しますか?
古くさい文章? 難しい漢字だらけ? それとも教科書に出てきた名前だけの存在?
今回ご紹介するのは、そんなイメージを吹き飛ばす“江戸のマルチタレント”、大田南畝(おおたなんぽ)です。
彼は、狂歌というユニークな詩の世界で笑いと風刺を届け、同時にまじめな幕府の役人としても働いていたという、まさに二刀流の人物。
この記事では、「大田南畝って結局なにをした人?」「どうしてそんなに有名なの?」「今でも読む意味あるの?」といった疑問に、
わかりやすく、面白く、そしてじんわり心に残る形で答えていきます。
笑って、なるほどと納得して、ちょっと感動もできる。
そんな“南畝ワールド”を、どうぞ気軽にのぞいてみてください。
江戸時代の「文化人」って?大田南畝の基本プロフィール
江戸時代の町人文化とは?
江戸時代の町を歩いてみると、にぎやかな商人の声、行き交う人力車、湯気の立つ屋台。
そんな中に「町人文化(ちょうにんぶんか)」というものが生まれました。
武士が支配していた時代にあって、町人――つまり商人や職人たちがつくり出した独自の文化です。
芝居や落語、浮世絵、そして狂歌(きょうか)など、身近でわかりやすく、ちょっとふざけた風刺や笑いを含む表現が人気を集めていました。
この文化の中で「大田南畝(おおたなんぽ)」も育ちました。
彼の作品は、まさにこの町人文化の中にぴったりフィットするものでした。
真面目なようでふざけていて、ふざけているようで核心をついてくる。
江戸の庶民が「わかるわかる!」と笑いながら読んだのです。
たとえば、今でいう「SNSでバズる」ような感覚。
人の心をつかむテンポの良い言葉と、ちょっとした皮肉。
それが狂歌やエッセイに乗って、江戸中に広まっていきました。
南畝が活躍したのは、まさにそんな自由で面白い文化の花が咲いた時代だったのです。
大田南畝の本名とペンネームの秘密
「大田南畝(おおたなんぽ)」という名前、じつはこれ、本名じゃありません。
本名は「大田覃(おおた・ふかし)」と言います。
少し難しい名前ですが、役人としてはこの本名で仕事をしていました。
でも、彼が狂歌や文芸の世界で活躍するときには「南畝」や「四方赤良(よものあから)」といった名前を使い分けていたのです。
まるで現代のペンネームや芸名のようですね。
たとえば「南畝」という名前は、「南の畝(うね)」と書きます。
この「畝」という字は、田んぼの畝のように何かを育てるイメージがあり、文化を耕す人という意味が込められていたのかもしれません。
一方、「四方赤良」はちょっとユニークなペンネーム。
「世の中すべてが赤い=酒びたり」という意味をこめた名前とも言われています。
酒好きだった南畝らしいユーモアがにじみ出ていますね。
こうした名前を使い分けながら、まるで役者のように文芸の世界とお役所の世界を行き来していたのです。
名前にも、当時の自由な発想と遊び心が詰まっているのが面白いですね。
役人としての仕事もしていた!
「文人」として有名な大田南畝ですが、実はれっきとした幕府の役人でした。
若いころから学問に優れていた彼は、役所勤めの仕事にも熱心に取り組んでいたのです。
とくに南畝は「勘定所」や「町奉行所」などの役所で、記録や報告書をまとめるような文書仕事に長けていました。
当時の役所仕事といえば、今でいう「公務員」。
真面目な仕事の合間に、狂歌を書いたり文章を書いたりしていたなんて、なんだか意外ですよね。
昼間はまじめな役人、夜はユーモアたっぷりの文人。
まるで昼はスーツ、夜は芸人――そんな二面性を持つ人物だったんです。
しかも、南畝はその文才を活かして、幕府の公式な記録や文章の作成にも関わっていました。
地味に見えるけれど、文化の担い手としてとても重要なポジションだったのです。
現代でいえば、官僚でありながら人気ブロガーでもあるような存在。
そのバランス感覚が、南畝という人物の魅力のひとつです。
どうして有名になったの?
では、なぜ大田南畝はこれほど有名になったのでしょうか?
きっかけは「天明の狂歌ブーム」でした。
あるとき江戸の町では、難しい和歌ではなく、庶民でも楽しめる「狂歌」が大流行。
言葉遊びと風刺に満ちたこのジャンルで、南畝は圧倒的な人気を集めました。
たとえば、当時の流行や社会問題をちょっと茶化した一首。
それが多くの人の共感を呼び、「よくぞ言ってくれた!」と喝采を浴びました。
しかも、南畝の狂歌は読みやすく、テンポがよく、記憶にも残りやすい。
いわば、江戸の「バズるポエム」だったのです。
さらに彼は文章でも力を発揮し、エッセイや日記でも人気を博しました。
とくに『浮世床』『浮世百話』といった作品は、今でいう「コラム」や「ブログ」に近く、町人たちの日常をリアルに描いていました。
ただの詩人ではなく、時代の空気をつかむセンスが抜群だったからこそ、多くの人に愛されたのです。
今でも評価されている理由
200年以上も前の人なのに、なぜ大田南畝はいまでも注目されているのでしょう?
それは、彼の書いたものが「古びない」からです。
南畝の作品には、ユーモア・皮肉・風刺という、時代を超えて通じるエッセンスが詰まっています。
たとえば、政治への不満、物価の高騰、職場のストレス。
現代とあまり変わらない悩みを、彼は笑いに変えて書いていたのです。
その姿勢は、現代の漫才やSNSの風刺漫画にも通じるところがあります。
また、南畝の文章はとても読みやすく、親しみやすい言葉づかい。
堅苦しい文語体ではなく、リズミカルな語り口が特徴です。
読んでいるうちに、まるで江戸の町を一緒に歩いているような気分になる。
そんな「情景が見える」文章だからこそ、時代を越えても人を引きつけるのでしょう。
そして、笑いとともに「本質」を見つめる視点。
それが今の私たちにも「なるほど」と気づかせてくれるのです。
代表作に見る!南畝のユーモアと風刺のセンス
狂歌ってなに?
「狂歌(きょうか)」って、初めて聞くとちょっとこわい言葉に思えるかもしれません。
でも実はとてもユーモラスで、誰でも楽しめる言葉遊びの詩なんです。
狂歌とは、五・七・五・七・七のリズムで作る短い詩。
一見すると和歌と同じ形式ですが、内容がまったく違います。
恋の切なさや自然の美しさを詠む和歌に対して、狂歌は「日常の面白さ」や「世の中の皮肉」をテーマにします。
たとえば、友達とのすれ違いをおもしろく書いたり、政治や物価のことをちゃかしたり。
現代でいえば、Twitterの大喜利や、風刺漫画に近い存在かもしれません。
しかも、狂歌は堅苦しくない。
むしろ、庶民がくすっと笑えるくらいの、やさしい表現で書かれていました。
大田南畝はこの狂歌の世界で大活躍します。
難しいことをやさしく、つまらない日常を面白く。
それができたから、たくさんの人に愛されたのです。
「四方赤良」って名前に込められた意味
大田南畝にはたくさんの別名がありますが、中でも「四方赤良(よものあから)」という名は、特に有名です。
この名前、一見するとちょっと変わった響きですよね。
実はここにも、南畝らしいユーモアが詰まっているんです。
「四方赤良」とは、「四方=世の中すべて」「赤良=赤ら顔の酒好き」という意味にかけているとされます。
つまり、「酒に酔って赤ら顔になっている自分が、世の中を見回して書いている」という風刺のメッセージが隠されているのです。
なんだか、酔っ払いが世の中をじっと見つめながら「おかしいよなぁ」とつぶやいているような情景が浮かびますね。
この名前には、自分が「偉い人」ではない、むしろ「庶民の視点」で語っているというスタンスがにじみ出ています。
まるで居酒屋の片隅で話しているおじさんが、実はめちゃくちゃ鋭いことを言ってる。
そんな空気感が、南畝の名前にも作品にもあふれているのです。
有名な狂歌をいくつか紹介
大田南畝の狂歌は、いま読んでも思わず「ぷっ」と笑ってしまうほど絶妙です。
その中でもとくに有名な一首をご紹介しましょう。
世の中は 何にたとえん 山彦の こたふる声は こなたより出づ
これは「山びこ」に例えて、「世の中の反応って、自分の声が返ってくるだけだよね」という意味をこめています。
現代のSNSで「炎上」したり「バズ」したりする様子に似ていませんか?
また、こんな一首もあります。
春風や 猫も杓子も 浮かれ出づ
これは「春になると、猫も杓子も――つまり、誰も彼もが浮かれだす」という様子を、春の気分にかけて描いたものです。
季節の情景と庶民の気分が重なって、まるで今の花見シーズンのよう。
こうした狂歌は、言葉のセンスだけでなく、人の気持ちに寄り添う視点があってこそ生まれるのです。
短い言葉で「あるある」を切り取る。
それが、南畝の真骨頂です。
庶民の暮らしを笑いで描くってどういうこと?
江戸時代、庶民の暮らしは決して楽ではありませんでした。
飢饉もあれば物価高もあり、政治も混乱気味。
それでも人々は日々を生き、笑いを忘れませんでした。
大田南畝は、そんな庶民の生活の「リアル」を、笑いに変えて描きました。
たとえば、日々の小さな不満――米の値上がり、上司の理不尽、夫婦ゲンカ。
それらを狂歌にすると、不思議と明るく見えてくるのです。
「つらいけど、笑って受け流そう」
そんな気持ちにさせてくれる作品ばかり。
これは、現代のお笑い芸人が、社会のストレスを笑いに変えて届けるのと似ています。
南畝の狂歌には、「一緒に笑おう」「お前だけじゃないぞ」というやさしいメッセージが込められているのです。
それが、200年経った今でも心に響く理由かもしれません。
現代のバラエティ番組に似てる?
大田南畝の狂歌や随筆を読んでいると、まるで今のバラエティ番組を見ているような気分になることがあります。
笑いがあって、共感があって、ちょっとした風刺もある。
そんなテンポの良さと、ちょっぴり毒のあるユーモア。
たとえば、南畝が書いた『浮世床』や『浮世百話』は、江戸の人々の会話をそのまま切り取ったような作品。
まるで街中の井戸端会議や、立ち飲み屋での雑談をのぞき見しているような感覚です。
「こんな人、いそう!」と思わせるキャラクターの会話がテンポよく続き、読み手を飽きさせません。
まさに江戸のトーク番組。
しかも、それがただのおしゃべりで終わらないのが南畝のすごいところ。
その中に社会の風刺や、人の本質への問いかけが潜んでいるのです。
「笑いながら、ちょっと考える」
これは、今のテレビやネット番組にも通じる、大切なエンタメの形ですね。
大田南畝は文才だけじゃない!多才な活躍ぶり
漢詩や随筆もこなすスゴさ
狂歌で有名な大田南畝ですが、実は彼の才能はそれだけではありません。
南畝は「漢詩(かんし)」もよく書いていたんです。
漢詩とは、中国の漢字を使った詩で、厳格なルールと深い意味が必要とされる、ちょっと格の高い文学。
まるで、軽快な漫才をする芸人が、クラシック音楽も弾けるような感じです。
狂歌ではおどけた言葉遊びを楽しんでいた南畝が、漢詩になると一転、静かで繊細な詩を詠む。
まるで月明かりの下で、物思いにふける詩人のようです。
また、随筆――つまりエッセイや日記も得意でした。
『浮世床』や『半日閑話』といった作品には、日常の一コマを面白く、かつ深く描いた文章が並んでいます。
南畝の随筆は、どこか落語に似ていて、読みながら登場人物の声が聞こえてきそうな臨場感があるのです。
どんなジャンルもこなせるその柔軟さ。
それが南畝をただの文人ではなく、時代を超えて愛される「表現者」にしていたのです。
翻訳や記録もできる万能人
大田南畝の仕事は、ただ「面白いことを書く人」だけではありませんでした。
じつは、当時の外交や技術にも関わるような翻訳や記録の仕事にも携わっていたのです。
たとえば、長崎奉行所に勤務していたころには、オランダや中国からやってくる情報を記録したり、外国語を扱ったりする場面もありました。
今でいえば、外務省と文化庁を兼ねたような仕事ぶり。
文章を書く力がある人は、情報を正しく伝えることにも長けている。
その代表例が南畝でした。
また、江戸のさまざまな事件や出来事を記録する役割も任されていました。
彼が残した記録は、今の歴史研究にも役立っているんです。
ふつう、こういう仕事は地味で目立たないものですが、南畝はそれすらも「面白く」記録してしまう。
たとえば事件簿でも、堅苦しい文ではなく、どこか人物の心情までにじむ描写がある。
それはまるで、新聞記者と小説家を兼ねたような才能です。
江戸の「オタク」的存在?
南畝の興味は、とにかく幅広かった。
狂歌、漢詩、随筆、翻訳……それだけでなく、落語や歌舞伎、そして庶民の言葉や行動までも、彼は観察しては記録に残していました。
一言でいうと、まさに「江戸のオタク」的存在。
好きなものをとことん掘り下げて、人に伝えるのが得意だったのです。
たとえば、町人たちの話し方や流行の遊び。
普通の人ならスルーしてしまうような細かい言い回しや仕草にまで目を配り、それを文章に書きとめていました。
これは、現代でいうカルチャー研究家やYouTuber、あるいは民俗学者のような感覚。
ただ面白いだけではなく、「残しておきたい」「伝えたい」という情熱が、彼を突き動かしていたのかもしれません。
物事を深く見つめる目と、それを伝える力。
それは、オタク的情熱から生まれた、本物の知性だったのです。
幕府に仕えながら文化を広めた役人
「文化人」と聞くと、自由気ままな生活を思い浮かべるかもしれません。
でも南畝は違いました。
彼は幕府に仕える役人という立場を持ちつつ、文化の発信も続けた人物です。
つまり、「会社勤めしながら趣味で本を出す」ような二重生活を送っていたのです。
昼間はお役所でまじめに記録や調査。
夜になると筆をとり、江戸の暮らしや社会の裏側を、笑いとともに描く。
南畝の周囲にも、同じように詩や文章を書いて楽しむ仲間がいて、彼らと連れ立って「狂歌会」を開いたり、「筆談」で言葉遊びをしたり。
その交流から、新たな作品やアイデアが次々と生まれていきました。
立場は公務員、でも心は自由なクリエイター。
それを両立できたからこそ、南畝は「市民に愛される文人」になったのです。
旅の記録もユニークだった!
南畝は旅もよくしていました。
そして、その旅の記録がまた面白い。
まるで「旅ブロガー」のように、自分の見た風景、出会った人々、感じたことをユーモラスに書き残しています。
とくに『蜀山人行状記』や『壬申紀行』などの作品では、彼の旅のようすがいきいきと描かれています。
旅先での小さなハプニングや、その土地ならではの言い回し、おかしな風習などを見つけては、独自の視点で紹介。
たとえば、ある地方の料理を食べて「江戸の猫も食べまい」と書いて笑いにしたり、宿の主人とのやりとりを落語のように描いたり。
そこには、ただの記録ではない「物語」があります。
旅をしながらも、人の心や世の中を観察している。
どこにいても、ユーモアと探究心を忘れない姿勢。
それが、南畝らしい旅のスタイルだったのです。
江戸庶民の代弁者?大田南畝の生きた時代背景
江戸時代後期ってどんな時代?
大田南畝が活躍したのは、江戸時代の後期――おおよそ18世紀後半から19世紀初頭のことです。
この頃の江戸の町は、一見するとにぎやかで豊かな時代でした。
商人が力を持ち、町には屋台や見世物小屋、芝居小屋が立ち並び、人々の生活には笑いや遊びがあふれていました。
しかし、その一方で大きな問題も潜んでいました。
幕府の財政は苦しく、庶民の生活にもじわじわと負担が増えていきます。
特に大きな影響を与えたのが「天明の飢饉(てんめいのききん)」。
これは1780年代に起こった、深刻な食糧不足の時代です。
飢えや病に苦しむ人々が増え、町は混乱と不安に包まれていきました。
それでも、そんな時代の中で人々は知恵と笑いを頼りに、なんとか毎日を生き抜いていました。
南畝の狂歌や随筆は、そんな時代の空気の中から生まれてきたものです。
表面は明るくても、背景には重たい現実があった。
それを知ると、彼の作品のユーモアに、さらに深みが感じられます。
天明の飢饉と社会不安
1782年から始まった「天明の飢饉」は、大田南畝の人生と作品に大きな影を落とした出来事です。
冷害や洪水が続き、米が取れなくなり、物価は高騰。
江戸の町でも、ごはんを食べられない人が増えました。
農村では餓死者が出て、町でも物乞いが増え、治安も悪化していきます。
まるで、夜になると灯りがすべて消えて、静まりかえった町に、うす暗い影が動くような、そんな重苦しい雰囲気だったのでしょう。
このとき、幕府は改革を進めようとしますが、それが庶民にとっては逆効果になることもありました。
贅沢を禁止されたり、物価を無理に下げられたり。
苦しいときに、さらに息苦しくなるような政策に、人々の不満は高まっていきました。
そんな中で、南畝のような文人たちが、狂歌で「ちょっと毒のある笑い」を投げかける。
それは、直接的な反抗ではなくても、「こんな時代だって、笑ってやろうぜ」という庶民の強さを表していたのかもしれません。
南畝の作品に映る市民の本音
南畝の狂歌や随筆には、当時の庶民の本音が、びっしりと詰まっています。
たとえば、こんな一首。
倹約は よいことなれど むつかしや 腹へり声を 笑ひにかへる
意味は、「倹約はいいことだけど、空腹の声を笑いに変えるのは、なかなかむずかしい」。
これは、まさに飢饉や物価高の中で、我慢を強いられる人々の気持ちを、そのまま代弁したような言葉です。
南畝は、「庶民のことば」を使って、庶民の目線から社会を見つめました。
だからこそ、読む人は「わかるわかる」と思いながら、クスリと笑えるのです。
それは、現代でもSNSで「自虐ネタ」が共感を呼ぶのと似ています。
誰かが自分の代わりに本音を言ってくれる。
それをユーモアで包んでくれる。
南畝の作品は、そうした「代弁者」としての力を持っていたのです。
為政者への風刺って危なくない?
当時の江戸幕府は、権力の頂点にありました。
そんな中で、政治や社会への「風刺」を書くなんて、ちょっと危険なことのように思えますよね。
実際、幕府はたびたび言論の自由を制限し、書物や芝居にも目を光らせていました。
けれど南畝は、そのギリギリのラインを見極める「笑いの技術」を持っていたのです。
たとえば、直接「この政治はダメだ」と言うのではなく、町の出来事や庶民の会話に仮託して、そっと皮肉を差し込む。
それはまるで、トランプを一枚ずつめくるように、観客にヒントを渡していく手品師のようです。
読者は「ああ、そういうことか!」と気づき、共感し、心の中で拍手を送る。
それが、南畝流の風刺でした。
真っ向から戦うのではなく、笑いという包み紙で伝える。
そのバランス感覚が、彼の作品を今も輝かせている理由のひとつです。
なぜ庶民に愛されたのか?
南畝が庶民にこれほどまでに愛された理由。
それは、彼が「同じ目線」に立って物事を語っていたからです。
彼は役人としてそれなりの地位にいましたが、常に庶民の暮らしや悩みに寄り添い、それを理解しようとしました。
そして、その気持ちをユーモアと共に言葉にして届ける。
それは、ただの文人ではなく、「心の近くにいる語り手」だったからこそ、できたことでした。
たとえば、お寺の境内で子どもたちが笑いながら遊ぶ姿。
母親たちが井戸端で話す声。
魚屋のにぎわい。
そうした日常の中から、彼の言葉は生まれました。
笑いを通して「おまえもがんばれよ」と背中を押してくれるような存在。
南畝の人気は、作品の面白さ以上に、その「人としてのあたたかさ」にあったのかもしれません。
現代に活きる南畝の魅力とは?
笑いと風刺の重要性
今の世の中、情報があふれていて、毎日いろんなことが起きています。
ニュースを見れば、不安な話やイライラする出来事が次々に飛び込んでくる。
そんな時代だからこそ、「笑い」や「風刺」の力が、より大切になってきていると思いませんか?
大田南畝が生きた江戸時代も、決して平和で気楽な時代ではありませんでした。
飢饉、貧困、政治への不信感――現代とよく似た問題が、そこかしこにあったのです。
そんな中で、南畝は狂歌という形で「ちょっと笑える、でもちょっと刺さる言葉」を発信していました。
それは、今でいう風刺コントや、皮肉のきいたツイートのようなもの。
まじめすぎず、でも核心をつく。
笑いがあるからこそ、読んだ人の心にスッと入り、いつの間にか考えさせられている。
言葉の力って、すごいですよね。
現代でも、ユーモアのある言葉が人の心を救うことがあります。
その意味で、南畝のような存在は、時代を超えて必要とされているのかもしれません。
読みやすくて今でも面白い理由
大田南畝の文章や狂歌は、200年以上前に書かれたにもかかわらず、いま読んでもびっくりするほどわかりやすいのです。
その理由のひとつは、「庶民のことば」を使っているから。
難しい漢字ばかり並んだ書物とは違い、南畝の言葉には、生活の音やにおい、人の気配が宿っています。
たとえば、子どもが駆けまわる夕暮れの路地裏。
その向こうから聞こえてくる魚屋の呼び声。
そんな風景を、南畝の文章はさりげなく描いてくれます。
しかも、ただの描写では終わりません。
「そうそう、こういうことあるよね」と、読者が共感し、思わず笑ってしまう仕掛けがしっかりある。
まるで落語を聞いているような感覚です。
テンポがよく、リズムが心地よい。
だから、現代人にもスッと入ってくる。
「昔の文章=堅苦しい」と思っている人にこそ、南畝の作品はおすすめです。
教科書だけじゃもったいない!
大田南畝の名前、実は学校の教科書で見かけることもあります。
でも、それだけで終わらせてしまうのは、ちょっともったいない。
なぜなら、南畝の魅力は「学問」ではなく、「暮らしの中で感じる面白さ」にこそあるからです。
たとえば、お笑い番組で取り上げられそうなネタ。
あるいは、友達との会話で生まれる笑いの種。
そうした身近な感覚が、南畝の作品にはぎっしり詰まっているのです。
試験のために覚えるだけの人物ではありません。
読んで、笑って、そして少し考える。
そんな「体験型の文学」として、もっと自由に楽しんでいいんです。
本屋でふと南畝の名前を見かけたら、「あ、あの面白い人だ」と思い出して、手に取ってみてください。
きっと、思いがけない発見がありますよ。
南畝から学ぶ「自由な発想」
南畝の作品を読んでいると、「こんな自由な考え方、いいなあ」と感じる瞬間がたくさんあります。
決まりきった表現にとらわれず、日常の中のちょっとした違和感や可笑しさをすくい取って、言葉にする。
それはまるで、型にハマらない芸術家のようです。
たとえば、物事を真面目にとらえすぎて苦しくなっているとき。
「別の角度から見れば、こんなに面白いじゃないか」と言ってくれるのが南畝。
頭が固くなりがちな現代の私たちにとって、その視点はとても新鮮です。
失敗もネタにする。
不満も笑いに変える。
そうやって「自由に考える力」が、南畝の作品から伝わってくるのです。
それは今の社会において、仕事や勉強、そして人間関係においても、すごく大事なヒントになると思います。
令和にも必要な「ユーモアの力」
令和の時代に生きる私たちは、常にスマホやネットの情報に囲まれ、早いスピードで変わっていく毎日を生きています。
そんな時代だからこそ、ふと立ち止まって笑える瞬間が、心の支えになることがありますよね。
大田南畝のような「ユーモアを持った視点」は、現代人にも大切な力だと感じます。
たとえば、ちょっとしたミスで落ち込んだ日。
SNSで見た嫌なニュースに疲れたとき。
そんなとき、南畝の狂歌のような言葉が、「まぁ、そんな日もあるよ」と肩の力を抜かせてくれるかもしれません。
笑いは、人をつなげる魔法です。
そして、笑いには「心の回復力」もある。
それを200年以上も前に教えてくれていた南畝の存在は、まさに今こそ再発見すべき文化財ではないでしょうか。
大田南畝とは何をした人?まとめ
大田南畝という人物は、一言では語り尽くせないほどの魅力に満ちた存在です。
狂歌を中心に活躍した文人として知られていますが、その活動は漢詩、随筆、記録、翻訳、さらには旅の記録まで、じつに多岐にわたっていました。
江戸時代後期――混乱と不安が渦巻く社会の中で、彼は庶民の視点を持ちながら、「笑い」というフィルターを通して物事の本質を伝えました。
それはまるで、現代のコラムニストや風刺芸人のような役割。
彼の作品は、当時の人々にとっての救いであり、楽しみであり、そしてちょっとした「ガス抜き」の場でもありました。
南畝のすごいところは、形式やジャンルにとらわれない「自由な発想」にあります。
漢詩でも狂歌でも、役人としての記録でも、どこかに彼の遊び心と人間へのまなざしが感じられます。
そして、その作品たちは、今なお私たちの心に響く力を持っています。
笑いに包まれた言葉の奥に、時代の真実が宿っている。
大田南畝の存在は、今を生きる私たちにこそ必要な「ユーモアと観察力の天才」と言えるでしょう。