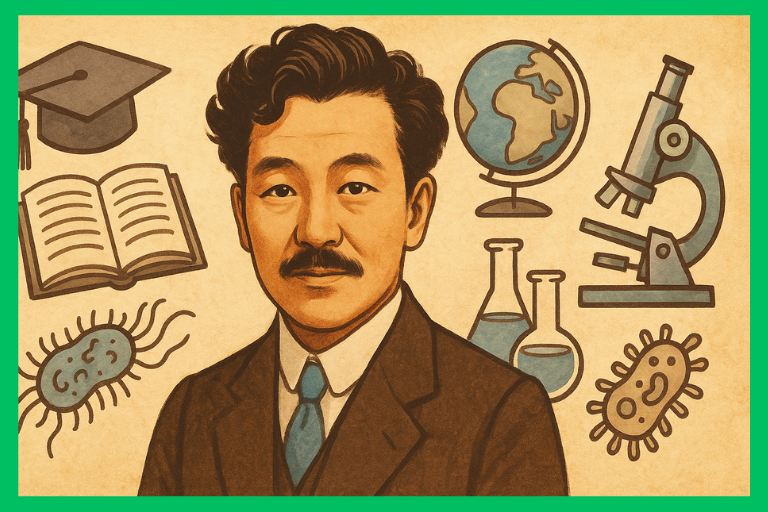千円札の顔として有名な野口英世。でも「結局、何をした人?」と聞かれると、うまく一言で言えない人も多いはずです。
英世は、ただの天才ではありません。貧しさ、左手の不自由さ、言葉の壁、命の危険。それでも逃げずに、感染症の正体を突き止めようとしました。
この記事では、まず結論を短く押さえたうえで、英世がどんな道を通って世界の研究者になったのか、そして黄熱病で評価が割れる理由まで、やさしく丁寧にまとめます。
読み終えたころには、「英世ってこういう人だったんだ」がスッと腹落ちするはずです。
野口英世は「何をした人?」を30秒で簡単に
最重要ポイントだけ解説
野口英世は、病気の原因を調べる「細菌学」の研究者です。福島の貧しい農家に生まれ、幼いころの大やけどで左手が不自由になりながらも勉強を続け、医師資格を取り、やがてアメリカで研究の第一線に立ちました。
特に梅毒などの感染症研究で注目され、最後は黄熱病の研究のために西アフリカへ行き、現地アクラで黄熱病に感染して51歳で亡くなりました。
ここで大事なのは、「千円札の人」だから偉い、ではなく、当時こわがられていた感染症に対して、実験と観察で答えを出そうとした研究者だった、という点です。
今みたいに薬や検査が整っていない時代、病気はまさに命の問題でした。だから野口英世の人生は、勉強の努力だけでなく「人を救うために、わからないことを解き明かす」挑戦の連続だったんです。
いちばん有名な功績は何?
いちばん有名なのは、「感染症の原因となる微生物を、実験で確かめる研究」を、世界の中心で続けたことです。
とくに梅毒に関わる研究は、当時とても大きなテーマでした。国会図書館の人物解説では、ロックフェラー医学研究所で梅毒スピロヘータの純粋培養を行ったことが紹介されています。
ただし、歴史上の科学はいつも一発で決着するわけではありません。ある研究が「当時の最先端として評価された」ことと、「後の時代の技術で見直したら修正点が出る」ことは両立します。
野口英世がすごいのは、正解だけを拾ったからではなく、難しい病気に対して現場と実験で迫り、世界中が注目するほどの量と熱量で研究を積み上げたことです。
「千円札の人」で終わらない3つの実績
野口英世を「何をした人?」で押さえるなら、まずはこの3点がつかみやすいです。
| ざっくり一言 | 何がすごい? |
|---|---|
| 研究で世界に出た | 日本から渡米し、世界の研究の中心で成果を出した |
| 梅毒など感染症の研究 | 当時深刻だった病気の原因解明に挑んだ |
| 黄熱病に命がけで挑戦 | 1928年にアフリカへ渡り、現地で感染して亡くなった |
さらに補足すると、初期には蛇毒研究でも評価され、そこから研究者としての道が開けたことが公的な紹介でも触れられています。
つまり「天才が最初から無双した」というより、「評価されるテーマをつかみ、成果で道を切り開いた」タイプなんです。
どんな時代に、何が求められていたのか
野口英世が生きたのは、感染症が社会を揺さぶっていた時代です。今なら予防接種や衛生管理、検査キットが当たり前ですが、当時は「原因がわからない」「うつる仕組みも不明」「治療法も少ない」病気がたくさんありました。だから研究者の仕事は、いま以上に切実でした。
野口英世は、日本で医師資格を得た後、伝染病研究所などを経て研究の道を強め、海外へ向かいます。公的な年譜や人物紹介を見ると、医術開業試験の合格、研究所での勤務、渡米、ロックフェラー医学研究所での研究と、流れがはっきりしています。
ここがポイントで、野口英世は「町医者として診察する」より、「研究で多くの人を救う」方向に舵を切った人物として理解すると、行動がつながって見えます。
簡単に読みたい人へ最後に
最後に、いちばん大事な心構えをひとつ。野口英世は「成功だけの人」ではありません。
黄熱病の原因については、当時の仮説と後の理解にズレがあり、評価が割れる部分もあります。だからこそ、歴史人物として面白い。すごさも、弱さも、まるごと見たほうが「何をした人か」が立体的にわかります。
挫折から医学へ:左手の大やけどが人生を変えた
1歳ごろの事故で左手に大やけど(ここから始まる)
野口英世(幼名:清作)は、1876年11月9日に福島で生まれました。
幼いころ、囲炉裏に落ちて左手に大やけどを負ったことが、人生の大きな分かれ道になります。公的な紹介では「1歳半の時」とされていて、ここははっきり押さえておきたい事実です。
やけどの何がつらいかというと、痛みだけではありません。手が思うように動かないことで、生活も勉強も、周りとの関係も難しくなるからです。子どもの世界は残酷で、ちょっとした違いがからかいの種になります。
けれど清作は、そこから逃げるのではなく、「勉強で負けない」という方向に気持ちを向けていきます。ここが、野口英世の物語が多くの人の心をつかむ理由のひとつです。
学びを支えた人たち(先生・家族・周囲の力)
努力は一人でもできます。でも、続けるには支えてくれる人が必要です。野口英世の場合、それが母のシカや、恩師の小林栄先生でした。内閣府の紹介では、清作の才能を見出した小林先生が進学を勧め、学びを支えた流れが説明されています。
ここを「美談」として終わらせるのは簡単ですが、現実はもっと泥くさいはずです。お金がない、道具もそろわない、家の手伝いもある。しかも手は不自由。そんな状況で成績を上げるには、気合だけじゃ足りません。周りの大人が「この子は伸びる」と信じて、具体的に動いたことが大きい。
つまり野口英世の成功は、本人の根性だけでなく、教育の力と支援の力が合わさって生まれた、と考えると納得感が増します。
手術で「できる」が増えた瞬間(15〜16歳ごろ)
清作は16歳の時、会津若松の会陽医院で医師の渡部鼎(わたなべ かなえ)に左手の手術をしてもらい、親指が動くようになったと記念会の展示説明にあります。物が持てるようになった感動が、医学のすばらしさを体で理解する体験になり、「自分も医学の道へ」と決意するきっかけになりました。
ここで注目したいのは、「完治」ではない点です。公的な紹介でも、手術はしたが完治はしなかった、とされています。つまり不自由さは残ったまま。
それでも「前よりできることが増えた」ことが、人生の選択を変えた。これって、いまの私たちにも通じます。夢が一気にかなう瞬間より、小さな回復や小さな成功が、次の挑戦のエネルギーになることがあるからです。
劣等感が“原動力”に変わった考え方
コンプレックスは、放っておくと自分を傷つけます。でも、使い方を変えると武器になります。野口英世の人生を見ていると、「見返したい」「負けたくない」という気持ちが、勉強と挑戦の燃料になっているのがわかります。内閣府の紹介でも、貧しさや不自由さの中で勉学に励み、成績を修めた流れが語られています。
もちろん、劣等感がある人が全員うまくいくわけではありません。大事なのは、気持ちの矛先を「自分や他人を傷つける方向」に向けず、「昨日の自分を超える方向」に向けることです。
野口英世がすごいのは、境遇のせいで腐るのではなく、勉強という行動に変換したところ。感情を行動に変える力は、才能というより、くり返しで育つ技術です。今日からできる一歩は小さくていい。ノート1ページ、英単語10個でも、積み上げは裏切りません。
ここが胸アツ:努力が空回りしないコツ
努力が空回りする時って、「何を目指すか」がぼやけている時です。野口英世の場合は、手術の体験で目標が一気に具体的になりました。「医者になりたい」ではなく、「医学で人を救う側に行きたい」という実感が入ったからです。記念会の説明でも、手術の感動が医学への志につながった流れが示されています。
空回りしないコツを、清作の流れに合わせて3つにするとこうです。
- 目標を体験で固める→憧れより、実感のほうが強い。
- 環境を変える→学べる場所、支えてくれる人の近くへ行く。
- 小さな勝ちを積む→完璧じゃなくても「昨日よりできた」を積む。
清作が次に進むのは、会陽医院で学びながら医師資格を目指す道です。ここから東京へ出て、医術開業試験、済生学舎、研究所へと進みます。続きの章では、その具体的なルートを、当時の制度も含めてわかりやすく説明します。
日本での修業:医師資格より「研究」で人を救う道へ
上京して医師の試験に挑戦(当時の仕組みをやさしく)
野口英世は、いきなり大学の医学部へ進んだわけではありません。明治の日本には、医師として働くために国の試験に合格する道があり、英世もそのルートで資格を得ています。国立国会図書館の人物解説では、済生学舎に学び、1897年に医術開業試験に合格した、と整理されています。
ここが「簡単に」知りたい人にとってのポイントです。つまり英世は、家が豊かでなくても、学び方を工夫して医師への道を切り開いた人でした。上京後は生活費を稼ぎながら勉強し、試験に挑んでいます。
野口英世記念会の展示解説でも、高山歯科医学院で働きつつ、受験準備のために済生学舎にも通った流れが書かれています。
当時の試験は、いまの受験みたいに「学校に行けば自動的に資格がもらえる」仕組みではありません。だからこそ、学ぶ人は自分の生活と勉強を両立させる必要がありました。
英世のすごさは、頭が良いだけでなく、学ぶ環境を自分で作る力にあります。さらに言うと、ここで身につけた「知らないことは調べて、確かめて、また修正する」という姿勢が、のちの研究者としての土台になります。
勉強の拠点:済生学舎で何を学んだ?
済生学舎は、当時、医術開業試験を目指す人が多く学んだ場所として知られています。国立国会図書館の解説にも、英世が済生学舎に学んだことが明記されています。
では、そこで何を得たのか。ざっくり言うと「医師として必要な基礎」を、試験に耐える形で鍛えた、ということです。人体の仕組み、病気の考え方、薬や衛生の知識など、診療の入口になる内容を、短期間で必死に吸収していくイメージです。
英世は左手に不自由さが残っていたので、ノートの取り方一つでも工夫が必要だったはずです。それでも前に進めたのは、学びを「才能」ではなく「技術」にしていたからだと思います。
記念会の展示では、英世が高山歯科医学院で働き、鐘を鳴らす係などをしながら勉強したと説明されています。
このエピソードは地味ですが、現実味があります。勉強は、机に向かえる人だけのものではありません。仕事の合間、寝る前の数十分、移動の途中。そういう時間を積んだ人が、最後に伸びます。英世の東京時代は、そういう積み上げの教科書みたいな時期です。
医師になったのに開業しなかった理由
1897年に医師資格を得た英世は、そのまま町で開業して患者さんを診る道も選べたはずです。けれど実際は、高山歯科医学院や順天堂医院などで働き、のちに伝染病研究所へ進んでいきます。記念会の年表や展示、国会図書館の解説でも、勤務先と研究所への流れが示されています。
理由を一言で言うなら、「診察」より「研究」に心が向いたからです。感染症が猛威をふるう時代、目の前の一人を診ることも大事ですが、病気の原因や広がり方を解明できれば、もっと多くの人を救えます。
英世は、まさにそちらへ賭けた人でした。そこには、幼いころに手術で救われた体験も影響したでしょう。医学の力を体で知っているからこそ、「まだ分からない病気を減らしたい」という気持ちが強くなったのだと思います。
もう一つ現実的な話をすると、開業には資金や人脈、道具が必要です。英世の家は豊かではなく、東京で生活しながら勉強してきた背景があります。研究所や病院で働くことは、生活を支えながら専門性を高める道でもありました。理想と現実の両方を見たうえで、英世は研究者としての道を選び取っていきます。
伝染病研究所で“研究者モード”に入る
1898年ごろ、英世は北里柴三郎が関わった伝染病研究所に入り、細菌学の研究者を志す方向がはっきりします。国会図書館の解説に「伝染病研究所を経て」とあり、記念会の年表でも助手としての勤務が示されています。
研究所での経験は、医師としての勉強とは別の意味で大きいです。病気を「治す」だけでなく、「病気がどう起きるか」を、実験と観察で確かめる世界に入るからです。細菌学では、目に見えない微生物を扱います。培養して増やす、顕微鏡で見る、動物実験で確かめる。やることは地道で、失敗も多い。でも、その積み重ねが社会を変える力になります。
内閣府の紹介では、伝染病研究所時代に通訳や案内役をしたことが、のちの渡米につながったと説明されています。
つまり研究所は、技術だけでなく「世界につながる扉」でもありました。英世は、偶然の出会いを、ちゃんと次の行動につなげられる人です。運が良いだけではなく、運を活かす準備をしていた、という感じですね。
名前を「英世」に変えた背景(短く要点だけ)
英世はもともと「清作」という名前でした。それが1898年ごろに「英世」へ改名します。内閣府の紹介では、坪内逍遥の小説『当世書生気質』に出てくる「野々口精作」という人物に自分を重ね、生活を改める決意をして、恩師の小林栄と相談のうえで改名した流れが語られています。
この話は、ただの小ネタではありません。名前は、他人に見せる看板でもありますが、自分自身への約束でもあります。「これからはこう生きる」と決めると、人は行動が変わります。英世の場合は、研究の道へ進む時期と重なっているので、改名はスイッチの役目を果たしたと考えると分かりやすいです。
まとめると、英世の東京時代はこう整理できます。
| 時期の流れ | やったこと | つながった先 |
|---|---|---|
| 上京 | 働きながら勉強 | 医術開業試験の合格 |
| 医師資格取得後 | 病院勤務 | 現場感覚と基礎固め |
| 研究所 | 細菌学へ | 海外へ挑戦する土台 |
| 改名 | 決意を形に | 行動の方向が定まる |
世界で勝負:アメリカで成果を出した研究(蛇毒・梅毒など)
渡米後のスタート:助手として食らいつく
1900年、英世はアメリカへ渡ります。内閣府の紹介によると、伝染病研究所時代に面識のあったペンシルベニア大学のサイモン・フレキスナーを頼っての渡米でした。
この時点で、英世は英語も完璧ではなく、資金も十分ではありません。ここがまず現実的にすごい。普通は怖くて止まります。でも英世は、怖さより「世界で研究したい」が勝った。
渡米直後の仕事は、いきなり華やかな研究ではなく、助手的な立場からのスタートです。内閣府の紹介では、蛇毒研究で月8ドルほどの報酬だった、という具体的な記述まであります。
ここで想像してみてください。不自由な左手で毒蛇を扱う作業は、危険のかたまりです。それでも英世は、成果を出せば道が開けることを知っていた。自分が勝負できる分野に集中して、まずは研究者として認められることを最優先にした。海外で生き残るための戦い方として、かなり合理的です。
蛇毒研究で一気に注目されるまで
英世がアメリカで評価を高める入口になったのが蛇毒研究です。ロックフェラー・アーカイブセンターの人物紹介でも、ロックフェラー研究所での最初の仕事が蛇毒研究だったと述べられています。
ここで大事なのは、蛇毒研究が「派手で面白いテーマ」だっただけではなく、当時の医学にとって実用性が高かった点です。毒の仕組みが分かれば、治療や血清の研究につながるからです。
英世は、実験の手数が多く、とにかく仕事量で押すタイプでもありました。ロックフェラー研究所での人事情報や関連アーカイブでは、フレキスナーと密に働いたこと、免疫学やスピロヘータ(らせん形の細菌)などへ研究が広がったことが触れられています。
蛇毒で信用を得て、次に大きな感染症へ。研究者としての階段の上り方がうまいんです。もちろん、ここに努力と粘りがないと話になりません。海外の研究室は結果がすべて。結果を出した人だけが次のテーマに進める。その世界で英世は前へ進みました。
ロックフェラーで研究を続けた理由と環境
英世は1904年からロックフェラー医学研究所(当時)で研究を続け、亡くなるまでその一員として働きます。ロックフェラー・アーカイブセンターの紹介では、1904年に研究所へ来て、助手からメンバーへと役割を上げていったことが書かれています。
ロックフェラーの何がすごいかというと、研究に集中できる環境です。実験に必要な設備、試薬、動物、仲間、議論の相手。それがそろうと、研究のスピードが上がります。英世は、まさにその環境で「大量に実験し、すぐ検証し、すぐ次へ進む」スタイルを爆発させたわけです。
ただし、環境が良いと、逆に弱点も目立ちます。研究は、量だけでなく、再現性や慎重さも必要です。英世については、成果が大きい一方で、結論を急いだ面が指摘されることもあります。ロックフェラーのコラムでも、英世は多作であった一方、梅毒の原因の発見者と誤解されることがある、という趣旨の注意が書かれています。
ここは、英世を「完璧な天才」としてではなく、「強烈な推進力を持った研究者」として見ると理解しやすいです。
梅毒の研究で何がすごかったのか
梅毒は、当時とても恐れられていた感染症です。原因となる菌はトレポネーマ・パリダム(Treponema pallidum)で、これが体に入り、長い時間をかけて深刻な症状を起こすことがあります。英世の研究の大きな功績のひとつは、梅毒が進行して脳に影響を与える状態(麻痺性認知症など)との関係を、病変部から菌を見つけることで示した点です。ブリタニカは、英世が麻痺性疾患の患者の脳でトレポネーマを見つけたことを紹介しています。
さらに、1911年には梅毒スピロヘータの純粋培養に成功したとされ、国会図書館の解説にもその記述があります。
野口英世記念会のページには、1911年の論文「病原性トレポネーマの純粋培養法」など、実際の論文情報が一覧で掲載されています。
ここで「純粋培養って何?」を中学生向けに言うと、他の菌が混ざらない状態で、狙った菌だけを育てることです。これができると、原因を確かめたり、検査法や治療の研究を進めやすくなります。だから当時は非常に注目されました。英世は、難しい菌に対して方法を工夫し、世界が驚く成果として提示した。そこが大きいんです。
“論文マシーン”の働き方:強みと弱み
英世の特徴は、単発の大発見というより、実験と発表の量で研究を押し進めたところです。ロックフェラー・アーカイブセンターの紹介でも、蛇毒から免疫学、梅毒、黄熱病などへ広く研究したことが述べられています。
研究対象が広いのは、好奇心が強い証拠でもありますし、社会の課題に反応してテーマを選べた証拠でもあります。
ただ、スピードが速い人は、転び方も派手になります。英世が黄熱病に関して「細菌が原因」という仮説を追ったことは、ロックフェラー財団アーカイブの解説でも、誤った結論だったと整理されています。
この弱点は、責めるためにあるのではなく、学びの材料です。科学は「最初から正解を知っている人」が勝つゲームではありません。仮説を立て、実験で確かめ、外れたら直す。その繰り返しで前に進みます。英世は、当時の限界の中で必死に答えへ近づこうとし、最後は命を落としました。
だからこそ、英世から学べるのは「挑戦し続ける姿勢」だけではありません。「結果が出た時ほど、疑って確かめる」「熱量が高いほど、落とし穴にも気づく」という、研究にも勉強にも共通する教訓です。次の章では、その黄熱病への挑戦と最期、そして評価が分かれる理由を、逃げずに分かりやすくまとめます。
黄熱病への挑戦と最期:功績・限界・今につながる話
黄熱病とは何が怖いのか(当時の切迫感)
黄熱病は、蚊が運ぶウイルスが原因で起こる感染症です。感染すると、発熱や頭痛から始まり、重くなると黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)や出血、臓器のダメージが出ることがあります。
いちばん怖いのは、流行が起きると短期間で多くの人が倒れる点です。今でも「流行しやすい病気」として扱われ、ワクチンで防げる一方、地域によっては対策が追いつかないこともあります。
当時は、病気の正体をつかむ道具も限られていました。原因がウイルスだと分かっていても、目で見えない相手をどう確かめるのかが難しい。
さらに、蚊をどう管理するか、現地でどう安全に検体を集めるか、医療体制が十分でない場所でどう研究するか。机の上だけでは進まない、現場のしんどさがついて回ります。だから黄熱病研究は、命に関わる危険な仕事でした。野口英世は、その一番怖い現場に、あえて入っていった人です。
現地調査で何をしようとしたのか(狙いを整理)
野口英世が黄熱病研究に深く関わるのは、南米や中米での調査を経て、最後に西アフリカへ向かった流れの中にあります。英世は黄熱病の原因について、ある細菌(レプトスピラの一種)を疑い、患者の検体から「Leptospira icteroides」を分離したと報告しました。内閣府の資料でも、1919年にこの菌を分離したことが「学術上の業績」として紹介されています。
英世の狙いは単純で、「原因をつかめば、予防や治療の道が開ける」という発想です。だから、患者の血液や臓器、動物実験を使って、菌がいるかどうかを確かめ、培養(増やすこと)にも挑みました。実際、英世自身の論文も残っていて、当時のやり方で必死に証拠を積み上げようとしていたのが分かります。
ただ、ここで大事なのは「当時の最先端で真剣にやった」という事実と、「結論が最終的に正しかったか」は別だということ。英世は、現場の切迫感の中で、手持ちの技術で答えに迫ろうとしました。その姿勢は本物です。でも、研究の世界では、姿勢だけでは勝てない瞬間もあります。次でその話をします。
なぜ評価が割れるの?(後にわかったことも含めて)
野口英世の黄熱病研究が評価の分かれ道になる理由は、黄熱病の原因が「細菌ではなくウイルス」だと確立していったことにあります。WHOやCDCは、黄熱病が蚊によって運ばれるウイルス感染症であると明確に説明しています。
つまり、英世が追っていた「Leptospira icteroides」が黄熱病そのものの原因だった、とは言いにくい。英世の仮説は、結果として外れに近い側に寄ってしまいました。
さらにややこしいのは、当時は似た症状の病気も多かったことです。黄疸が出る病気は黄熱病だけではありません。英世の菌が、黄熱病ではなく別の病気(レプトスピラ症など)に関係していた可能性が、当時から指摘されていました。古い医学雑誌の記事ですが、英世の菌とレプトスピラ症の菌の類似を指摘する議論が残っています。
このあたりが「英世は間違えた」で終わらない難しさです。現場では診断も完全ではなく、研究も今ほど精密ではない。だから、当時の研究者たちは、限られた条件の中で最善を尽くし、時に遠回りしながら真実に近づいていきました。
ここから得られる教訓はシンプルです。科学は「正しい人をほめる大会」ではなく、「間違いも含めて、次の精度を上げていく営み」だということ。英世の黄熱病研究は、その現実を強烈に見せてくれます。
アクラで亡くなるまで:命がけの研究の現実
野口英世は西アフリカのアクラで黄熱病研究を続け、1928年5月21日に黄熱病で亡くなりました。内閣府の英世年譜でも、アクラで研究中に黄熱病にかかり、51歳で亡くなったことが明記されています。
「研究者が研究対象の病気で命を落とす」これはドラマみたいに聞こえるかもしれませんが、当時の感染症研究では現実に起こり得たことでした。
ここで想像してほしいのは、英世がどれだけ怖かったか、です。自分が倒れたら研究は止まる。仲間にも迷惑がかかる。家族にも会えない場所で、体調が崩れていく。にもかかわらず、英世は現場に残り、最後まで原因に迫ろうとしました。
もちろん、勇気だけで片付けるのは危険です。安全対策は最優先であるべきですし、今の研究現場ではその考え方が徹底されています。でも、英世が生きた時代には、今ほど整った仕組みがありませんでした。だからこそ、英世の最期は「医療や研究の安全の大切さ」を考えるきっかけにもなります。
そしてもう一つ。英世が亡くなった事実は、「失敗した研究者だから」ではなく、「危険な病気と真正面から向き合った研究者だったから」起きたことです。そこは、評価の土台として外せません。
今の私たちに残ったもの(アフリカ賞・学び・誤解の解き方)
野口英世が残したものは、研究成果だけではありません。英世の名は、いまも感染症と闘う人をたたえる賞に受け継がれています。日本政府は2006年7月に「野口英世アフリカ賞」を設立し、アフリカの感染症対策や医療サービスの仕組みづくりに貢献した人を表彰しています。
ここがすごく象徴的です。英世が命をかけた場所はアフリカで、その名が、アフリカの健康と命を守る活動を支える形で生き続けている。
そして、英世から学べることは「努力」だけじゃありません。
私は特に、この3つが現代向けの学びだと思います。
- 正しいかどうかは、最後まで検証する(熱量が高いほど要注意)
- 現場に行く(机上の知識だけで分からないことがある)
- 間違いが出ても、次に活かす(科学も勉強も更新が前提)
英世の黄熱病研究には、外れた部分がありました。でも、それを隠すのではなく、良い点も弱い点も見たうえで「じゃあ自分はどう学ぶ?」に変える。これが歴史人物を読むいちばん強い読み方です。英世は、偉人というより、挑戦の仕方を教えてくれる先輩です。
野口英世についてまとめ
野口英世は「感染症の原因を調べる研究者」で、福島の農家に生まれ、幼少期の左手の大やけどを乗り越えて学び続け、医師資格を得て、やがてアメリカで研究の中心に立ちました。
蛇毒研究で評価をつかみ、梅毒などの研究で注目され、最後は黄熱病研究のために西アフリカへ行き、アクラで黄熱病に感染して51歳で亡くなりました。
黄熱病の原因については、英世の仮説が後に修正される部分もあり、そこが評価の割れる点です。
でも、その事実ごと含めて、英世の人生は「未知に挑むこと」「検証し続けること」「危険な現場で人を救おうとすること」を強く感じさせます。そして、その精神は野口英世アフリカ賞のような形で、いまも世界の医療に受け継がれています。
【参考資料】
・野口英世の生涯 : 野口英世アフリカ賞 – 内閣府
・野口英世博士:野口英世アフリカ賞 – 内閣府ホームページ
・野口英世|近代日本人の肖像 | 国立国会図書館
・公益財団法人 野口英世記念会
・“Noguchi, Hideyo” by The Rockefeller Archive Center